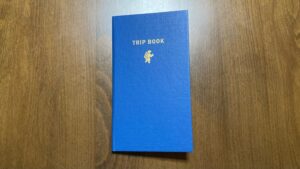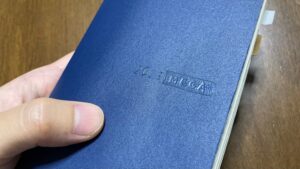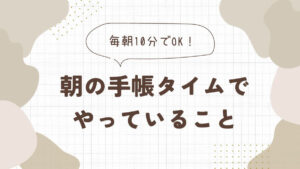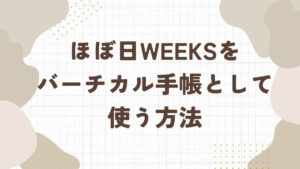【読書感想】感情的にならない気持ちの整理術
精神科医である和田秀樹先生著の「感情的にならない気持ちの整理術」を読みました。
感情をコントロールできなくて不機嫌になっている人は多いです。
でも大切なのはその感情をなくすことではなくて、自分の感情に振り回されないようにすること。
- 不機嫌やストレスを消すテクニック
- ごきげんな自分になるためのテクニック
これらを教えてくれる本です。
今回はこの本の感想をご紹介します!
感情的になってしまう心と脳の仕組み
ここでは10の基本が紹介されていますが、中でも自分が特にと感じた2つをまとめます。
感情に振り回されてはいけない
たとえマイナス感情であっても感情を持つこと自体が悪いわけではありません。
感情的にならない気持ちの整理術 P27
実は、マイナスの感情は人間を成長させる原動力ともなるからです。
「感情的にならないように」というと、どうしてもそのマイナスの感情を抑えようとしがちです。
でも、筆者はその感情自体が悪いものではないと述べています。
なぜならマイナス感情は、ときに人間を成長させてくれるからです。
ただし、マイナス感情をコントロールできないと、例えば勉強が手につかなくなってしまったり、緊張しすぎてパニックになってしまったりと、よくないことも起きてしまいます。
感情をコントロールできるようになるとこういったことがなくなるので、自分の思ったような生活を送ることができるようになるのです。
自分はいまどんな表情をしているか?
感情をコントロールできず、いつも不機嫌な人は、気むずかしくてムッとした表情をしています。
感情的にならない気持ちの整理術 P30
不機嫌な顔をしていると、当然周りの人も近づきたくありません。
そうすると、敬遠されて周囲からの評価も下がり、何をやっても上手くいかないという負のスパイラルに陥ります。
そういえば先日私も、子どもたちの朝の準備がなかなか進まずイライラしてしまいました。
すると仕事に出発する夫から一言、「もっと笑顔でいればいいのに」。
当然、そのときはバタバタしていたのでついイラッとしてしまいましたが(朝のバタバタでそんなこと言われたらイラッとしますよね。)、でも今思えば、たぶん相当不機嫌な顔をしていたんでしょう。
「今の自分はどんな感情を持っているか?」と自分の感情を確認する習慣をつけるとよいと著者は述べています。
こうすることで、自分がどんなときに不機嫌になりやすいのか傾向が分かるようになるのです。
感情的にならない考え方
心と脳の仕組みの基本を知ったところで、続いて感情的にならない考え方を見ていきます。
本で紹介されていた中から4つまとめます。
自分の性格の偏りに気づく
- 夫が家族で出かける時間のギリギリまで寝ている
- 子どもがおもちゃを片付けない
なぜだか他人の行動に無性にイライラしてしまうことってありますよね。
著者によると、これは自分が極端に時間に厳しかったりキレイ好きだったりするから。
性格が偏っているから相手の行動にいちいちイライラしてしまうのです。
この自分の性格の偏りを「あぁ、自分は極端にキレイ好きな性格なんだな」と認めてしまえば、他人の行動も冷静に受け止められるようになり、感情的にならずに済みます。
とはいえ、夫にはもう少し早く起きて欲しいし、おもちゃが散らかっているとどうしてもイライラしてしまいますよね…笑
自分へのご褒美を設定する
今週末は映画に行く予定!
帰ったら冷蔵庫に美味しいケーキが待っている!
このように、何か楽しみなことが控えていると気分もうきうきして、多少面倒で嫌なことがあっても乗り越えられるもの。
これを利用して、1週間に3回ぐらいのご褒美をあらかじめ作っておきます。
そうすれば、ごきげん気分を保つことができます。
これは大きな楽しみでなくても良くて、読書やスポーツ観戦、ディナーに行くなど、小さな楽しみでもOK!
以前、「毎日を楽しめる人の考え方」という本を読みましたが、この本にもあった考え方だなと感じました。
人によってご褒美は違うので、自分がうきうきワクワクするのはなんだったかな〜と考えるのも楽しいですね!
「自分を愛する気持ち」を持つ
毎日慌ただしく生活していると、小さな幸せになかなか気づくことができません。
でも、ふと振り返ってみると「今日も気持ちよく眠れた」「ご飯が美味しかった」など小さな幸せに気がつきます。
この小さな幸せを積み重ねていくと「今の自分は満ち足りている」と感じることができます。
そしてそれが「自分を愛すること」につながるのです。
「自分を愛する気持ちを持つ」ことができるようになると、毎日をごきげんで過ごすことができるようになると著者は述べています。
私は、毎朝3行感謝日記を書くようにしてから、小さな幸せに気がつくことができるようになりました!
自分を褒めるとご機嫌になれる
人は、ポジティブに肯定されると、実際にそうだと思い込む傾向があるようです。
これを、フォアラー効果やバーナム効果と言います。
普段の生活や仕事で褒められることはあんまりありません。
だから、自分で自分を褒めてあげればいいのです!
「今日は家事頑張った」「イヤイヤ期の子どもに付き合うの頑張った」「苦手な料理頑張った」などなど、どんなに小さいことでも構いません。
どんな結果が出たとしても、まずは自分を褒めることが大切です!
以前読んだ「心の容量が増えるメンタルの取扱説明書」では、これを「Ta-Da(じゃーん!)リスト」と呼んでいました。
私は朝の3行感謝日記と合わせて、夜にこのTa-daリストを書いて、今日1日の自分の「できた!」を日記に書くようにしています。
ストレスを増やす行動や考え方はやらない!
やってはいけないストレスを増やす行動や考え方。
自然とやってしまいがちです。
「察してほしい」は甘え!
これは主に夫に対してやってしまっています…。
帰宅する夫に対してついつい不機嫌な態度をとってしまう私。
(心の声)「一日中、子どもの面倒を見ていて大変だったの!それくらい察してよね!(心の声)」
朝なかなか起きてこなくて、やっと起きてきた夫に対して不機嫌な態度の私。
(心の声)「早起きして子どもの食事の支度やら身支度やっているんだから、自分の食事ぐらい自分で用意してよね!」
この「察してほしい」は甘え!!!
人の感情はちゃんと言葉にしなければ理解されません。
そもそも察してもらえなくて当然なのです。
ここは察して欲しいと不機嫌な態度をとってきた自分を反省するとともに、「察してもらえなくて当然」と割り切り、自ら不機嫌になることのないようにしたいと感じました。
毎日ご機嫌な自分でいるためには?
毎日ご機嫌な自分でいるために、どんなことができるのか?
「自分で変えられること」だけに取り組む
毎日ご機嫌な自分でいるためには、まず「自分で変えられること」だけに取り組むことです。
まずは「変えられること」と「変えられないこと」を分けます。
この「変えられないこと」は「過去と他人」。
例えば、勉強しない子ども。
親としてはやっぱり子どもには勉強をして欲しいから「勉強しなさい!」と言ってしまいがちです。
でも、勉強をするのは子ども自身。
親が子どもの代わりに勉強をすることはできません。
その代わり、子どもへの声かけの言葉を変えたり、親自身が率先して勉強をする姿を見せる、など自分の行動や姿勢を変えることはできます。
このように、自分で変えられないことには取り組まない、変えられないんだと理解するようにすれば、自然と気持ちも楽になります。
これはアドラー心理学の「嫌われる勇気」にもあった「課題の分離」と同じだなと感じました!
気分転換で感情を「上書き保存」する
人間には記憶したことを忘れる習性があります。
つまり、
どんなにイヤなことがあっても、新しい情報が上書きされればいつの間にか思い出せなくなってしまうのです。
感情的にならない気持ちの整理術 P165
ということは、イヤな記憶が引き出されないように上手に上書きをしていけば、毎日ごきげんでいられるというわけです。
イヤなことを忘れるためには、小さなToDoをどんどん見つけてやっていくのが良いと著者は述べています。
機械的にこなしていくことで、イヤな記憶が薄れていくというのです。
そんなにToDoリストが思いつかない!という人は、気分転換リストを用意しておくといいでしょう!
私の気分転換リストは、
- お昼寝する
- 甘いものを食べる
- 読書をする
- ストレッチをする
- 窓を開けて換気する
- 散歩する
合わせて読みたい本
今回は、和田秀樹著の「感情的にならない気持ちの整理術」をご紹介しました。
この他にも、本文でご紹介した最近読んでいいなと思った本をまとめておきます。